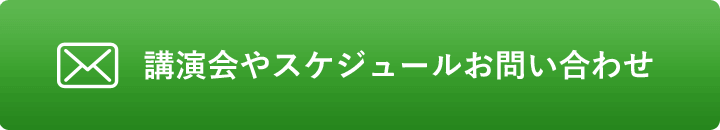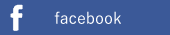![]()
沈黙と問いが育てる、心理的安全性のある組織
![]()

はじめに
現代の職場で注目されているキーワードの一つに「心理的安全性」があります。
簡単にいえば、「ここでは本音を言っても大丈夫」と思える空気のこと。これは、リーダーシップ、チーム運営、組織文化のすべてに深く関わる重要な要素です。
しかしこの「心理的安全性」、意識して作ろうとすればするほど、ぎこちなくなってしまうことも少なくありません。なぜなら、“話すこと”ばかりが強調され、“黙ること”の大切さが見落とされがちだからです。
沈黙は「不安」ではなく「安心」になれる
私は普段、僧侶として対話や講演の現場に立っています。そこでよく感じるのは、「沈黙を恐れずに共にいる」時間が、実は最も心が通じる瞬間だということです。
仏教には「無記(むき)」という教えがあります。すぐに答えを出さず、ただそのままを受け取ることをよしとする姿勢です。
上司や同僚が、部下やチームメンバーの言葉に対して「すぐに正す」「正論で返す」ことよりも、「沈黙で寄り添う」姿勢を持つことで、相手は“安心して話せる空間”を感じ始めるのです。

質問ではなく「問いかけ」が場を変える
対話の中で、私が大切にしているのは「問い」です。ただしこれは、「あなたはどう思いますか?」といった単なる情報収集の質問ではありません。
例えば、「最近、自分の中で落ち着かないことってありますか?」「この仕事に、あなた自身はどんな意味を感じていますか?」
そんな問いかけが、“対話の深度”を一気に変えていきます。表面的なやり取りから、個人の価値観や想いへと自然にアクセスできるからです。
安心できる場は、言葉でなく“態度”から始まる
心理的安全性とは、何か特別なノウハウを導入すれば得られるものではありません。
日々の沈黙、問い、受け止め方といった“見えにくい部分”が、少しずつ積み重なった結果として生まれるものです。
企業研修や組織支援の場では、そうした「目に見えないけれど、確かにある空気感」をどう育てていくか、仏教的な視点を交えてお話しています。
終わりに
職場とは、ただ仕事をする場所ではなく、人と人が支え合う「共生の場」です。
沈黙を恐れず、問いを持ち寄り、互いに安心して言葉を交わせる。そのような職場こそが、持続可能で力強いチームを育てていくのだと、私は信じています。

![]()

僧侶、理学療法士、プロファシリテーターとして個人相談をはじめ、集団での対話の場を作る(死生観カフェ、子育て座談会や仏教を学ぶ会など)。その活動がヤフートップ記事に取り上げられ、またNHK、女性セブンや日本経済新聞などにも掲載。パナソニックホールディングスにて「次の100年を考える」ゲストスピーカーとして登壇。シブヤ大学や教職員組合などの研修講師多数あり。
本コラムで紹介した「沈黙と問いで育てる心理的安全性のある組織」は、安心感ある対話や信頼関係を育むテーマとして、企業研修・管理職向け講演・チームビルディングセミナーでも高い関心を集めている内容です。心理的安全性や組織文化に関する講演をご検討の方は、Speakers.jpまでお気軽にご相談ください。
~鈴木秀彰氏への講演依頼、オンライン講演会企画のご相談は~
■お電話でのお問い合わせ
03-5798-2800
(受付時間9:30~18:30土日祝除く)
■FAXでのお問い合わせ
03-5447-2423
■メールでのお問い合わせ
https://www.speakers.jp/contact/
合わせて読みたい記事