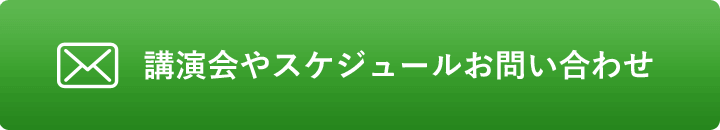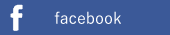![]()
働きがいと働きやすさをともに高める学校に
![]()

ジタハラが蔓延中?
学校、先生たちがすごく忙しいことは、よく知られるようになってきましたが、働き方改革は、うまく進んでいるでしょうか?
ここ数年の動きのなかで、わたしがすごく心配しているのは、多くの学校、教育委員会が時間外勤務時間を減らすこと、時短ばかりに注目しがちなことです。2025年6月には法改正まであって、時間外を月平均30時間以内にしていくという目標値ができたので、今後はよけい“圧”が強くなることでしょう。ジタハラ(時短ハラスメント)という言葉もあるくらいです。

先生たちにとっては、仕事は減らないのに、時間管理や数値目標ばかりやかましく言われて、やらされ感が募る。主体的になれずに受け身でストレスフルですよね。持ち帰りになって、残業の「見えない化」が進んでいることも問題です。
本来、勤務時間の管理や時短は、教職員の健康を守ることや人材獲得・離職防止などの手段の一部に過ぎないのに、手段が目的化してしまっています。
急がば回れ:対話と議論の時間をハショらない
関連して、みなさんと一緒に考えたいのは、働き方改革だからといって、つっこんだ話し合いをしたり研修したりする時間もバサバサカットして、大丈夫でしょうか。
もちろん、必要性の薄い会議や研修はやめたらよいし、進め方をもっと工夫すべきものもあると思います。とりわけ、小学校等で授業研究に偏りがちで、膨大な事前準備をしているところもあるのは、どうかと思います。いくら授業研究しても、いまは授業準備する時間がとれていないし、授業関連以外の不安や悩みもたくさんあるので。

一例ですが、若手の先生のなかには、「保護者に電話するのが怖い」いう人もいます。そりゃそうですよね、このネット時代に電話する機会は激減していますし。そんなちょっとした困り感や不安を開示して、ちょっとしたコツを教え合うような校内研修などがあってもいいと思います。
また、学校の業務のうち、どんなことは減らせそうか、変えられそうか、あるいは大切にしたいということを、教職員の間で話し合ってみてはどうでしょうか。働き方改革なんて、おおぎょうに言わなくてもいいです。自分たちの職場を自分たちでよりよくしていく活動なので。
もちろん、国や自治体で政策的に手を打たないといけないことも山積みです。学校にだけガンバレと申し上げたいわけではありません。とはいえ「アイツらが悪い」と言うばかりでは生産的ではありません。
教職員で困り感や気になることを持ち寄り、ちょっとした助け合いを進めつつ、職場改善策を練って、試行してみる。「お互いさま」や「ありがとう」を増やす。そんな主体的で対話的なチームづくりが、学校での働きがいと働きやすさを高める第一歩だと思います。

![]()

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年から独立。専門は学校マネジメント、学校改善、人材マネジメント、教育政策。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、文科省・GIGAスクール下での校務の情報化の在り方専門家会議委員なども多数経験。
本コラムで紹介した「学校現場で働きがいと働きやすさを高めるには」は、教育現場の働き方改革や教職員のチームづくりをテーマにした講演としても多く取り上げられている内容です。学校教育・働き方改革・組織改善に関する講演をご検討の方は、Speakers.jpまでお気軽にご相談ください。
~妹尾昌俊氏への講演依頼、オンライン講演会企画のご相談は~
■お電話でのお問い合わせ
03-5798-2800
(受付時間9:30~18:30土日祝除く)
■FAXでのお問い合わせ
03-5447-2423
■メールでのお問い合わせ
https://www.speakers.jp/contact/
合わせて読みたい記事