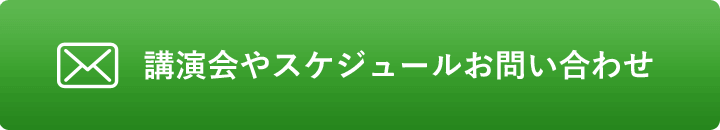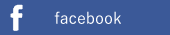![]()
「ツール導入=DX」という勘違いが会社をダメにする
![]()

はじめに
「クラウド入れたし、紙もやめた。なのに前より楽じゃない。」
そのモヤモヤ、原因は「DXの勘違い」かもしれません。
DXはカタカナの魔法ではなく、会社のやり方を良くして、お客さんの喜びと売上を増やすこと。
道具を並べるだけでは変わりません。
このコラムでは、よく言われている勘違いをスパッとほどき、今日からできるシンプルな進め方を紹介します。
まず何を整え、どこから小さく試し、どう“数字”で確かめるのか。
失敗を避けて成果に直結させるコツを、やさしく、具体的にお伝えします。
続きを読めば、「うちのDX、今どこでつまずいている?」がハッキリします。

勘違いその1:「ツールを入れればDX」
「クラウドを入れた」
「ペーパーレスにした」
「チャットやノートのアプリを導入した」
「生成AIを試した」
どれも大切ですが、これは「IT化」であって、DXそのものではありません。
IT化とは、仕事道具をアナログからデジタルに置き換えることだけではなく、それを専門的に扱える状態のことを指します。
しかし、世の中を見渡してみると、DXサービスの導入をするだけでDXができるといったようなことが語られています。
DXサービスを導入するだけで実現できるなら、日本中はDX成功事例ばかりです。
そうではないということは、DXサービスをいくら導入してもDXができないということを意味しているのです。
DXサービスに目がくらみ、まるでコレクションのように導入ばかりする。
しかも、専門的に扱えず、逆に労働生産性が下がってしまうことすらある。
このような状態になってしまうことも少なくありません。
DXの目的は、会社を強くすることです。
道具を増やすことではありません。
使い方も分からない調理器具ばかり増やしても、料理の腕前は向上しません。一流シェフなら、少ない調理器具でも結果を出すことができます。
これと同じく、ツールの数ではなく、「何をするのか」「どう使うのか」といったことの方が大事なのです。
では、何がよくなるとDXと言えるのでしょうか?
たとえば
「売上・利益が増える」
「お客さまがもっと喜ぶ」
「市場での強さが増す」
「商品やサービスの価値が上がる」
「提供方法が増える」
といったことができれば、DXを実現できていると見ることができるでしょう。

勘違いその2:「効率化=DX」
労働生産性を上げる取り組みは、IT化です。
書類をPCで管理する
はんこを電子にする
社内の相談をチャットにする
こういった取り組みは、作業効率を向上させる取り組みです。
その結果として、リードタイムの削減につながることもあるでしょう。
しかし、残念なことに、DXと全く無関係です。
データを活用できるパソコンスキルを持って、売り方・料金の決め方・組織の動かし方・お客さまとの関係のつくり直しまで踏み込み、会社を「別次元で強くする」取り組み。
これがDXなのです。
効率化をはじめとするIT化は、DXの前提条件です。
DXサービスをいくら導入してもDXできないのは、中途半端なIT化を行っているだけに過ぎないからです。
「導入すればDX」という宣伝や、「入れて終わり」という考え方に引っ張られると、短期的なコスト削減や効率化だけ見てしまいます。
そうなってしまうと、「本筋」を見失ってしまうのです。
その結果として、時間とお金を使ったのに、新しい売上も顧客の喜びも増えない。
これがよくある失敗の流れです。

失敗しないための超シンプル設計図
ここからは、ITが苦手でも今日からできる「失敗しない進め方」です。
1つ1つ丁寧に行うことで、余計な労力をかけずにDXを実現できます。
①何のためにDXをするのかを決める
まずDXを行う理由、目的を定めましょう。
DXは中長期にわたる戦いです。
この理由が辛い時期を乗り越えるカギになります。
この時、コスト削減だけは絶対にやめてください。
DXでコストの削減は実現できませんし、逆にコストが増える取り組みです。
お客様の満足度向上、シェア率向上、売上向上、従業員満足度向上など、このようなことを理由や目的に定めましょう。
②使うメインサービスを1つにする
DXサービスは同じカテゴリで複数サービス存在します。
ChatworkにLINEにSLACKに、Teams。
本当に多種多様なIT企業が同じようなサービスを提供しています。
なので、1つに絞りましょう。
1つに絞ることで、専門性を強化することが可能になります。
どんなによい道具でも使い方が分からなければ、使うことができません。
仕事道具なのですから、専門的に扱えて当たり前です。
そういった意味でも、1つに絞る勇気を持つのが大事です。
その中でもオススメは、Google WorkspaceとMicrosoft365です。
この2つの内、1つを使い倒すことをオススメします。
両方契約する必要性はありません。
③小さく試す
全社的に「よーい、どん!」は失敗します。
まずは小さく試していきましょう。
1つの部署、1つの課、1つのチーム、1つのプロジェクト。
このように小さな単位でできるなら、極力小さくやってみることをオススメします。
小さくやって、小さな成功体験を積んでいくことが大事です。
失敗しても痛手が少ないですし、再挑戦も簡単です。
失敗ゼロなんて不可能です。
失敗しても再挑戦できる状態で挑戦することが大事です。
④業務を棚卸する
意外に自分の業務を理解されている人は少ないです。
引継ぎをすると、なぜか劣化してしまうのは、こうした理由もあります。
なので、業務の棚卸をオススメします。
15歳くらいの高校生が明日来て、自分の業務を完璧に代行してくれるかどうか。
このレベルまで棚卸することができれば、IT化を進める上でも簡単になります。
どこをIT化できるのかを見極めるコツは、業務の棚卸にあるのです。
⑤情報を1つに集める
情報がバラバラに存在すると、データを扱うことが難しくなります。
そうなると、DXを実現できません。
個人パソコンにある情報もまた会社の資産です。
そのため、しっかり情報管理を行う体制を作ることが大事です。
そういった意味でも②で語ったように、サービスの統一を図り、情報管理を行いましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、DX推進で陥りがちな「ツールの導入」や「効率化」といった勘違いと、失敗しないための具体的な進め方をご紹介しました。
DXという言葉が先行し、「ツールを入れれば何とかなる」と考えてしまうのも無理はありません。
しかし、それだけでは決して成功しないのです。
本当に大切なのは、「何を作り出すのか」という目的意識と、道具を使いこなすための地道な努力です。
まず「何のためにやるのか」という目的を固め、一つずつ丁寧に業務を見直し、小さな成功を積み重ねていきましょう。
ぜひ、本記事でご紹介した「失敗しないための超シンプル設計図」を手に、未来へ向けた変革の第一歩を踏み出してください。

![]()

JAL・KDDI・無印良品といった大企業をはじめ、様々なプロジェクトに参画している15年以上のキャリアを持つ現役エンジニア。40歳で起業することを目標にしていたところ、当社の創設者に経営の勉強ができると誘われ、エストシステムズ社に入社。入社3日目で代表に選出され、以降社名を「皆人」と改めて経営者としてのキャリアをスタートさせる。
合わせて読みたい記事