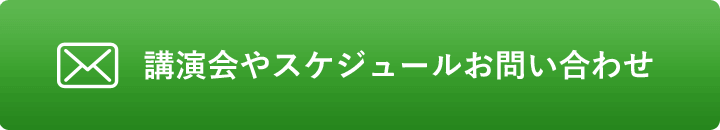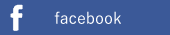![]()
立場も越えて、つながる職場へ
~組織活性のキーワードは“目線合わせ”~
![]()

組織活性・マネジメントの本質:「目線合わせ」と「諦め」
現代は、多様性が当たり前の時代。年代も価値観もバックグラウンドもバラバラだからこそ、会社の日常で「イライラ」「戸惑い」「誤解」が生まれやすくなっています。それは、「普通」「当たり前」がそもそも異なるから。また、会社が求めていること—とくに評価制度といったもの—が、上手く社員に伝わらない状況も珍しくありません。そこを突破する鍵が、“目線を合わせる”ことと、“諦める”ことです。

「目線合わせ」。これは理念や目的、あるいはその背景まで共通理解できているかということ。背景には育った時代や社会状況の違いが根深く影響します。出生年による価値観の違い、ジェネレーションによる感性の差…。まずは、世代間・個々の価値観を理解し合う場が必要です。そして同じ世代でも性格やライフステージが違えば価値観も異なる。だから「違いがあって当たり前」と心から思えるかどうか。これこそが、組織の第一ステップです。
そして「諦め」。これは、妥協して管理職や経営陣が諦めるという意味ではありません。「自分中心の常識」は諦めるという意味です。人それぞれの背景や価値観の違いを受け止めたとき、初めて、対話がスムーズに進みます。経営者・管理職側は特に、自社の評価制度や人事制度は「会社のため・社員のためにある」というWin‑Winの関係であることを、明快にコミュニケーションする必要があります。これが、個と組織のずれを埋めるスタート地点です。
なぜ違いが生まれるのか?:多様性の見える化と相互理解

では、世代・価値観・性格の違いは具体的にどこに現れるのか。その本質に迫るため、「出生年」「育った社会環境」「業務経験」「ライフステージ」といった軸で“違い”を言語化・見える化するワークを設計します。人事出身の視点から言えば、「言葉にされていない無意識の価値観」は、ときに業務上の溝や誤解を生みます。
具体的には、
- 若手:フラットなコミュニケーション、柔軟な働き方とフィードバックを重視
- 中堅:安定性と成果主義、結果に見合う対価を重視
- ベテラン:経験や過去実績、人間関係付加価値を重視
それぞれの関心や納得ポイントは違います。これを“場”で可視化し、「違いは矛盾ではない」「違いの理解は互いの尊重につながる」と毎回の研修・対話の中で体感してもらいます。その上で、「じゃあどう話す?」「どう制度を使う?」といった対話のフローを学び、実践力へとつなげます。
目線を合わせるための実践コミュニケーション術
では、どのようにして“目線を合わせ”、具体的な行動変容へとつなげるのか。本テーマを通じてご紹介するのが「評価制度理解⇄対話設計」です。言い換えれば、「会社が何を大切にしているのか」「評価軸は何か」「経営者の本音はどこにあるのか」という背景を、評価制度を使ったストーリーテリングで共有するのです。
ステップ 1
評価制度の目的・構造・背景を“物語化”して共有。評価軸は「会社視点」と「社員視点」を両立するものであることを、Win‑Winの文脈で伝える。
ステップ 2
実際の事例に基づくロールプレイやディスカッション。部署内の本音を見える化し、「どうすれば伝わるか」「違いをどう乗り越えるか」を対話を通じて学ぶ。
ステップ 3
継続フォローとして、定期的な振り返り(1on1・グループ対話)を設計し、「目線を合わせる文化」でPDCAを回す。こうしたプロセスを通じて、「あの人とずっと噛み合わなかったけど、今は信頼できる」「評価が腹落ちし、仕事のモチベーションも上がった」という組織変化を目指します。

組織の「変化」を実感できる講演・研修へ
この講演・研修では、単なる理論やテンプレートではなく、実践を通じた組織変革のステップをお伝えします。受講者がよく語るのは、「何となくもやもやしていたことに名前がついた」「あの人にイライラしていた理由が初めて分かった」という“言語化”の力です。組織における複雑な人間関係も、適切な対話と理解によって、少しずつ変化していきます。
特に中堅・管理職層にとっては、「伝える力」「聴く力」「共に考える力」が求められますが、それを自分らしく発揮するためには、自社の制度や仕組みへの“納得感”が欠かせません。「社長の頭の中がわかった気がする」「制度の意味が初めて腑に落ちた」という言葉が飛び出す瞬間は、まさに“目線合わせ”の成功例です。
このコラムを通して、組織に必要なのは「正解」ではなく、「対話の続く仕組み」であることを感じていただけたなら何よりです。そして、「私、村山に講演・セミナーをお願いしたい」と思っていただけましたら、とても光栄に思います。皆さまの組織がより活性化し、一人ひとりがいきいきと働ける環境づくりのお手伝いができればと願っております。

![]()

株式会社リクルートキャリアにて中小企業の採用支援に従事。魅力を打ち出しづらいニッチな業界でもその会社にいる人では気付けていない魅力を言語化・発信し、採用を成功させる。「人事部の救済者になりたい」「地方創生に貢献したい」という想いから独立し、現在は人事コンサルタント・組織プロデューサーとして活動の幅を広げている。
合わせて読みたい記事