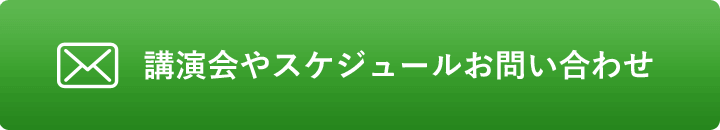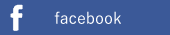![]()
子どもが「学校に行きたくない」と言い出す前にできること
― 不登校の“手前”にあるサインを見逃さないために ―
![]()

2025年4月、文部科学省が発表した調査によると、2023年度の小中学生における不登校児童生徒数は約34万6千人にのぼり、過去最多を更新しました。今や不登校は特別な誰かの問題ではなく、どの家庭にも起こり得る社会的なテーマです。
数字を見ると「深刻な社会問題」と感じられますが、その背景には一人ひとりの子どもの繊細な心の声があります。
「うちの子も学校に行けなくなったらどうしよう」
「クラスに通えない子がいるけど、どう接すればいいのか分からない」
保護者や先生から、そんな声をよく耳にします。

私自身も、数年ほど前に中学生だった息子が「学校に行けない」と言い出した経験があります。朝になると体調不良を訴え、布団から出られない。私は「ちゃんと行かないとダメでしょ」「頑張って行こう」と言い続けましたが、息子の顔はますます曇り、私自身も自分を責めて追い込まれていきました。
あんなに元気だったわが子が、ある日突然学校に行けなくなる。とても深い孤独感と不安を抱えて、悩みながら生活したあの日々は、今も忘れることのない、重たい経験です。だからこそ私は、不登校に至る「手前のサイン」に気づくこと、そして周囲の大人がどう関わればいいのかを、多くの方に伝えたいと思っています。
不登校は「ある日突然」ではない
「昨日まで普通に通っていたのに、急に行けなくなった」
そんな戸惑いの声をよく耳にします。けれど、不登校は前触れなく始まるものではありません。必ず数か月、あるいは数年も前から何かしらの「サイン」があるのです。

子どもが出している「不登校手前のサイン」
・朝になると、頭痛や腹痛を訴える
・学校や友達の話をすると、表情が曇る
・宿題に手をつけられず、ゲームや動画に没頭する
・イライラして家族に当たる、あるいは無気力になる
・「行きたくない」「もう疲れた」とつぶやく
これらは決して「怠け」や「わがまま」ではありません。むしろ、子どもの心が「もう限界だよ」「助けて」というSOSを発しているサインです。
不登校を防ぐ「3つのステップ」
私は自分自身の経験と、コーチングの実践から、次の3つのステップを提案しています。
ステップ1:過干渉をやめる
子どもに対して過剰に指示・命令だし、転ばぬ先の杖を与えすぎて過干渉になってしまっていませんか。「早くしなさい」「ちゃんとしなさい」という言葉は、子どもに「ありのままでは認められていない」と伝わります。少しずつ手を離して、子どもを信じて見守ること。それが“自分は大丈夫なんだ”という安心感につながっていきます。
ステップ2:子どもに向けていたエネルギーを自分に向ける
「子どものために必死になるあまり、自分がボロボロになってしまった」という保護者の声をよく聞きます。親が疲れているとイライラや焦りが子どもに伝わります。まずは親自身が休み、自分を満たすこと。それが家庭の空気を変え、子どもに安心感を与えます。
ステップ3:共感的なコミュニケーションをとる
コミュニケーションが、心の対話ではなく、指示や命令、交換条件の提示になってしまっていませんか。「行きたくない」と言う子どもに、「なんで?」と問い詰めるのではなく「行きたくないんだね」と気持ちを受けとめる。解決策がなくても「あなたは大丈夫だよ」という共感のメッセージが、子どもが心を開く大きなきっかけになります。
学校や先生方へのお願い
不登校は「行かない」ことが問題なのではなく、「行けないほど心が疲れている」ことに目を向ける必要があります。先生方も多忙で大変だと思いますが、子どもや保護者の声を受けとめていただけるだけで、どれほど救われるか分かりません。
保護者の方へのメッセージ
「自分の育て方が悪かったのではないか」
「周りにどう思われているだろう」
そんなふうに自分を責めてしまうお母さんは少なくありません。私自身もそうでした。
不登校は親や子どもが悪いわけではありませんし、ひとたび不登校を誰が悪いのかの指標で見てしまうと、本質から離れてしまいます。子どもは、ただ「心底安心できる場所がほしい」というサインを出しているのです。家庭が子どもにとって安心の場であれば、子どもは必ず回復していきます。親がまず自分を大切にし、子どもの気持ちをそのまま受けとめることで、子どもは再び一歩を踏み出す力を取り戻します。
おわりに ― 「不登校」は未来を閉ざすものではない
不登校は「失敗」ではなく、子どもが本当の自分を守り、自立していくためのきっかけとなります。その声に大人が気づき、受けとめることで、子どもの未来は大きく拓けます。
私の講演では、実際の体験談やコーチング事例を交えながら、
・不登校手前のサインの見つけ方
・子どもの心に寄り添う具体的な方法
・学校や家庭でできるコミュニケーションの工夫
をお伝えしています。
子どもたちが「自分は大丈夫」と安心して生きられる社会を、一緒に作っていけたら嬉しいです。

![]()

アメリカの四年制大学を卒業後、日本の特許事務所にてキャリアを積む。2児の母として子育てに向き合うなか、我が子の不登校という大きな壁に直面。親としての限界を痛感しながらも、再生の道を模索し、カウンセリング・児童心理・潜在意識コーチングなどを学ぶ。現在は、同じように悩む母親たちに向けて、「子どもの不登校を解決する3つのステップ」を基盤とした『キズナ再生プログラム』を提供。
合わせて読みたい記事