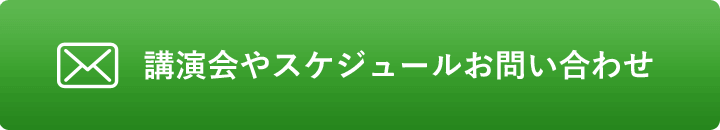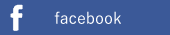![]()
都政は国政の先行指標と言われるが
![]()

間もなく都議選が!

よく都政の選挙、都知事選や都議選が近づくと「都政は国政の先行指標」と言われます。そうでしょうか?この6月22日には戦後21回目の都議選があります。
確かに89年の社会党躍進のマドンナブーム、93年の日本新党ブーム、01年小泉ブーム、そして05年の都議選後の小泉郵政解散と日本政治の大きな変化を占う指標でした。それは09年選挙の1ヵ月後の衆院選で政権交代へつながる。それも4年間で終わる。13年選挙では自公が復調し、過半数を超え、安倍1強体制がしばらく続いたが、昨年10月与党過半数割れに。今の小池都政をどうみるか、話題の石丸新党はどうなる。政治とカネ、SNS選挙が問わる中、パッとしない石破自民、足並みそろわぬ野党各党ですが、後半国会は次第に都議選、そして7月の参院選を睨みながら浮足立ってくるでしょう。
国民の1割、1000万人近い有権者の投ずる1票が東京から日本政治を揺るがしていく。
議員って何?
 よく、街の中や電車で胸に「議員バッチ」をつけている人を見かけるでしょう。赤紫、紫紺など丸いバッチ。国会議員も地方議員もみなこれをつけている。都議会の議員もそう。最近こそ減ったが、結婚式でも葬式でも「議員バッチ」をつけている人も少なくない。ひと目でこの人は議員だとわかる工夫だと言われればそうかも知れない。しかし、欧米などでは、こうした議員バッチなどつけている人はいない。そうした制度もない。バッチは韓国と日本など少数派です。
よく、街の中や電車で胸に「議員バッチ」をつけている人を見かけるでしょう。赤紫、紫紺など丸いバッチ。国会議員も地方議員もみなこれをつけている。都議会の議員もそう。最近こそ減ったが、結婚式でも葬式でも「議員バッチ」をつけている人も少なくない。ひと目でこの人は議員だとわかる工夫だと言われればそうかも知れない。しかし、欧米などでは、こうした議員バッチなどつけている人はいない。そうした制度もない。バッチは韓国と日本など少数派です。
もともと議員バッチは、議場への「通行証」としてつくられたもの。ですが、いつの間にか、一般人と区別する特権的な身分のあかし、「身分証」のように変わってしまった。議員バッチには特別な効用があるように見える。
胸元のバッチが”権威“の象徴にみえる。よく不祥事を理由に“責任をとって議員を辞職する”と会見した際、「議員バッチを外す」と言う議員がいる。自身にとって、議員バッチは命の次に大事なのでしょうか。ともかく日常、冠婚葬祭まで肌身離さず議員バッチを着け歩く姿を見ると、このバッチの存在が“議員とは何か”を考える際の重要なヒント、日本の政治文化をみる場合のポイントとなりそうですね。
地方議会で最大規模の議会、それが都議会。議員数は127名と飛びぬけて多い。その待遇も日本一でほぼ国会議員並み。しかし活動は?となる、とよく分からない。というのが一般の感覚ではないでしょうか。ちなみに都内には他に市区町村議員が1837名もいます。
都議会は私たち有権者に代わり、税金や条例を決める決定者、その使い道を監視する監視者、いろいろな解決方法を提案する提案者、その前提となる民意を集める集約者の4つの役割がありますが、ホントにそんな仕事をしているのでしょうか。

都議、都議会ご存知ですか

世論の声として一般に、地方議会は①民意を充分に反映していない、②政策立法活動が不十分、③行政への監視統制が不十分、④議員定数、議員報酬が多い、⑤女性やサラリーマンが少ない、といった批判があります。これって都議会にも当てはまるのでは?
静かなる議員集団127の都議会―これは一体どんな役割を果たしているか。当人に聞いてみると、まず驚くことに、都議会は「チェック機関」だと確信している議員が多いことです。条例案は知事ら執行機関が出す、予算は出されたものにイエス、ノーをいうのが議員の仕事だという認識です。条例案に修正を加えることもなく通す、予算の組み替えを求めることもない。議員の主な仕事は、年1回程度、本会議や委員会で質問に立ち、知事らの答弁を引き出すことだと考えているのでは。国会を見てもそっくりじゃないですか。
これが都議会の役割なのか。住民自治を代表する都議会は本来、都民の拠り所のはず。
しかし実際、様々なルートを通じ都民との対話を深めているのは知事ら行政側ではないか。
その程度の仕事しかしていない。なのに都議は非常勤の特別職公務員とされ、給与ではなく、報酬が払われる。1議員の月額報酬102万2千円。これに期末手当(ボーナス)が年間約4ヶ月分支給。これだけで年間約1700万円。それに1人当たり毎月60万円、年間720万円の政務活動費が支払われています。これは国会の立法事務費65万円とほぼ同額。また、都議会の会議に出てくると、1日当たり区部出身で1万円、多摩、島嶼出身では1万2千円が費用弁償として支払われる。これも本会議、委員会を含めると年間100万円近い。会議に出るのは労働じゃないのでしょうか。2重取りに感じがしません?
単純計算でも都議1人当たり合計約2500円が支給されていることになります。この待遇はほぼ国会議員並み。もちろん、生活費を含め様々な費用が掛かるので、本人から聞くと楽ではないというが、基本的に兼業兼職も認められる非常勤職なので、年100日程度の出勤日数の実態からすると、社会常識的には報酬としては「高い」のではないですか。 といった不満、疑問が蔓延しているのが議員をみる一般市民の目じゃないでしょうか。
3分の1入れ代わる、第1党も替わる
現在、都議会の議員は127名ですが、平均年齢は50歳と若く、当選回数も1,2回議員が6割を占めています。「通りやすく、落ちやすい」。どんどん入れ替わる、選挙のたびに概ね三分の一が入れ代わります。当選回数が少なく、ある意味で素人議員が多い。第1党も毎回入れ替わります。時に都民ファーストのような地域政党が台頭し、多くの議席を占めたりする。この夏にも地域政党「再生の道」が候補者擁立を進めており、旋風を巻き起こすのでは?と見る向きもあります。
数が多い、そうした根なし草のような素人議員の集団の間隙をぬうように、かつてはごく一部のボス議員が議会運営を支配してきた歴史もあります。都議会のドンと言われた自民党の長老や公明党のボスが全体を支配した時代もありますが、現在はそうした方々も亡くなり、都議会でのボス支配もなくなった。どうも「首都議会」と言いながら中身が薄っぺらな、風にそよぐ、ブームで動く「根なし草議会」のようにも見えますが、実際はどうなのでしょうか?

![]()
(マイナビ出版・)

1948年生まれ。早稲田大学卒業、早稲田大学大学院政治学研究科博士前期課程修了。東京都庁入庁、企画審議室などに16年間勤務。1989年3月、論文「都市行政学研究」で慶應義塾大学大学院より法学博士号取得。同年4月聖学院大学教授に転身。2018年4月から中央大学名誉教授、現在に至る。
合わせて読みたい記事